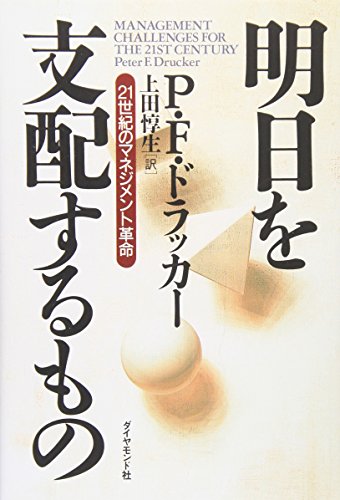知識労働の生産性は最低を基準としてはならない
日本とアメリカの違い
主語が大きいのは好きではないですが、 日本とアメリカを比べて、はっきり日本がダメだなぁということが1つあります。
それは、できない人を基準に考えているということです。
先日、アメリカのDevOps Engineerの求人を見てみました。 すると、結構な割合で、「コンピュータサイエンスの学位があること」が条件に入っていました。 H-1Bビザの関係が大きいと思いますが、専門の学歴がないとスタートにも立てないことが多いようです。
日本語圏の話を見ていると、できない人を基準に考えているなと思うことが多いです。
生産性は最低でなく最適が基準
ドラッカーの「明日を支配するもの」p170には以下のような記載があります。
知識労働の生産性は、仕事の質を中心に据えなければならない。 しかも、最低を基準としてはならない。最高ではないにしても、最適を基準としなければならない。 量の問題を考えるのは、その後である。このことは、知識労働の生産性向上には、 量ではなく質の面から取り組むべきことを意味するだけではない。 まずもって、仕事の質を定義すべきことを意味する。
すなわち、一番できない人を基準に考えてはいけないということです。 一番できる人でなくても、ある程度生産性が高い人を基準にする必要があります。
教育が鍵
ある程度生産性が高い人を基準にすると、どうしても生産性の低い人が出てきます。 これについては「教育」こそが重要です。
p181に以下のような記載があります。
次に、電話工自身に、架設と修理に分かれるべきか、 一人で何でもできるようにすべきかを考えさせた。答えは後者だった。 そこで小卒が平均だった彼らに、理論的な知識を与えることにした。 電話や交換機、さらには電話網の仕組みを教えた。 資格をもつ技術者や熟練工はいなかった。その彼らに、 十分な知識を持たせ、どのような問題についても原因を救命し、 対処できるようにした。そのうえテイラーの科学的管理法によって、 反復的な動作を正しく行えるようにした。
生産性の低い、スキルの低い人をそのままにするのではなく、 教育をすることによって知識を身につけさせ、専門家として働けるようにしました。
この場合は企業が必要性があって教育を行いましたが、 国策として行うのもアリだと思っています。
ドラッカーが度々取り上げていますが、 アメリカは「復員兵援護法」というのがあって、ある程度兵役をこなすと、 大学に行くための奨学金がもらえるようです。
日本にも形を変えて同じような制度があればいいのではと思います。
参考文献
←昔のツイートを削除しました
「問題管理」を始めてみた→